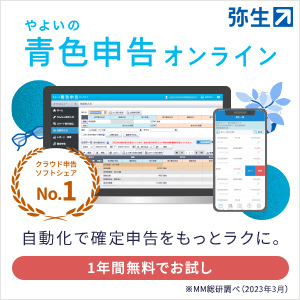厳選 ハンドプレス
電気工事で使うハンドプレスをご紹介させていただきますが、
通常のリングスリーブ用や裸端子用から絶縁閉端子用までご紹介いたしますので必要な物をご覧ください。
リングスリーブ用のハンドプレスは、あまり最近は使わなくなりましたが、外部のプールボックスでの接続や電源送り回路などは、リングスリーブによる圧着が望ましいと思います。
外部のプールボックスでの接続の場合、雨水の浸入や温度差による結露などが想定され、差込型コネクタでは絶縁不良になる可能性がございますので、リングスリーブを使って圧着接続し、自己融着Nテープを巻いた上に、ビニールテープで二重保護するのが望ましいと思います。
電源回路の接続の場合は、接続部分が引っ張られないように固定して、リングスリーブを用いて圧着するようにするべきです。
主に電源回路ケーブルの接続は天井内で行われることが多く、差込型コネクタでは、改修作業などで電源回路ケーブルが引っ張られて、コネクタから抜ける可能性があり、接続不良状態になった場合、発熱、発火の危険があるため、しっかり圧着し、接続部分を固定して保護する必要があります。
また、幹線ケーブルのように少し太めのケーブルでは、今でも圧着での接続が主流ですから、専用の圧着工具が必要です。
その他、絶縁閉端子の圧縮にも専用の工具が必要ですから、ここだけでも数種類のハンドプレスをご紹介することになりますので、私が使って使いやすいと感じてるものをご紹介させていただきますので、みなさんが圧着・圧縮工具をお選びになられる際の参考にしていただければと思います。
工事方法や使用環境を考慮して、適切な工法、工具を用いて、電気工事を安全に施工してください。
リングスリーブ用ハンドプレス
ロブテックス(LOBSTAR)
 ロブテックス(LOBSTAR) リングスリーブ用 AK17A |
 ロブテックス(LOBSTAR) リングスリーブ用 AK17MA2 |
|---|---|
マーベル(MARVEL)
 マーベル(MARVEL) リングスリーブ用 MH-17S |
 マーベル(MARVEL) リングスリーブ用 MH-7S |
|---|---|
ホーザン(HOZAN)
 ホーザン(HOZAN) リングスリーブ用 P-77 |
 ホーザン(HOZAN) リングスリーブ用 P-738 |
|---|---|
ここで紹介したほかにもデンサンの圧着工具も使いました。
その中でも、いち早く現在主流となっている形状と機構を備えたモデルを販売したマーベルの圧着工具を愛用してきたのですが、他社からも同じようなものが販売されるようになり、今では価格を比較して買うようにしています。
ここで紹介した大小2種類はリングスリーブ用ですが、見て分るように使用範囲が違うのと大きさもまったく違うので、私はほとんどリングスリーブ(中・小)対応のものを使っています。
小さくて邪魔にならないし扱いやすいので、
電気工事士技能試験にもおすすめの圧着工具です。
次は、裸端子用のハンドプレスを紹介しておきます。
裸端子用ハンドプレス
 マーベル(MARVEL) 裸圧着端子・スリーブ用 MH-38 |
 マーベル(MARVEL) 裸圧着端子・スリーブ用 MH-5S |
|---|---|
裸端子用の圧着工具はこの二つを使っています。
MH-38は、38sqまでのケーブルの接続用で、主に分電盤や配電盤への接続のときの裸端子を圧着するのに使っているもので、もう一つは制御盤などへの接続に使う小さな裸端子を取付けるのに使っていものです。
このほかに22sqまで対応の圧着工具も有るのですが、大は小を兼ねるということで私はMH-38をお薦めしておきます。
ハンドプレスタイプは、ご紹介している最小のものから最大60sq対応のものまであるので、必要な方は、Amazon、楽天市場の各ページのサーチボックスをご利用ください。
絶縁被覆付圧着端子用ハンドプレス
 マーベル(MARVEL)圧縮工具 絶縁被覆付圧着端子用 MH-155 |
 マーベル(MARVEL) 絶縁被覆付圧着端子用 MH-032 |
|---|---|
絶縁被覆付圧着端子用のハンドプレスを2本ご紹介させていただきましたが、普通の電気工事だけなら2本も必要ないと思いますので、私はMH-155だけを持っています。
もう一つのほうは、どちらかといえば盤屋さんとかが使うものだと思うので、普通の電気工事では扱わないようなケーブルサイズなのであまり必要ないでしょう。
次は同じ絶縁でも閉端子用のハンドプレスです。
閉端子とは具体的には下の画像のものです。
ニチフ 絶縁被覆付閉端接続子 CE形 CE1
弱電の接続などによく使われていますので、今更ご紹介するまでもなかったかもしれませんね。
それでは、これを圧縮するためのハンドプレスをご覧ください。
絶縁被覆付閉端用ハンドプレス
 マーベル(MARVEL) 絶縁閉端接続子用 MH-125 |
 マーベル(MARVEL) 絶縁閉端接続子用 MH-128 |
|---|---|
絶縁閉端子は、放送設備や火報関連の弱電屋さんがよく使うものですが、電気工事でも一部弱電の接続をすることもあるので、持っておかないといけない圧縮工具です。
これも両方持つ必要はなく、私はMH-125だけを持っています。
いくら絶縁閉端を使うといっても、せいぜいCE-5までですから、それ以上のものは必要ないのでMH-128は持っていません。
でも必要なら、持っておかないといけないので、そのときはMH-128だけを買えばいいでしょう。
どの工具でも仕事に必要な物を厳選して、無駄な工具を増やすことは、避けるようにするべきだと私は考えます。